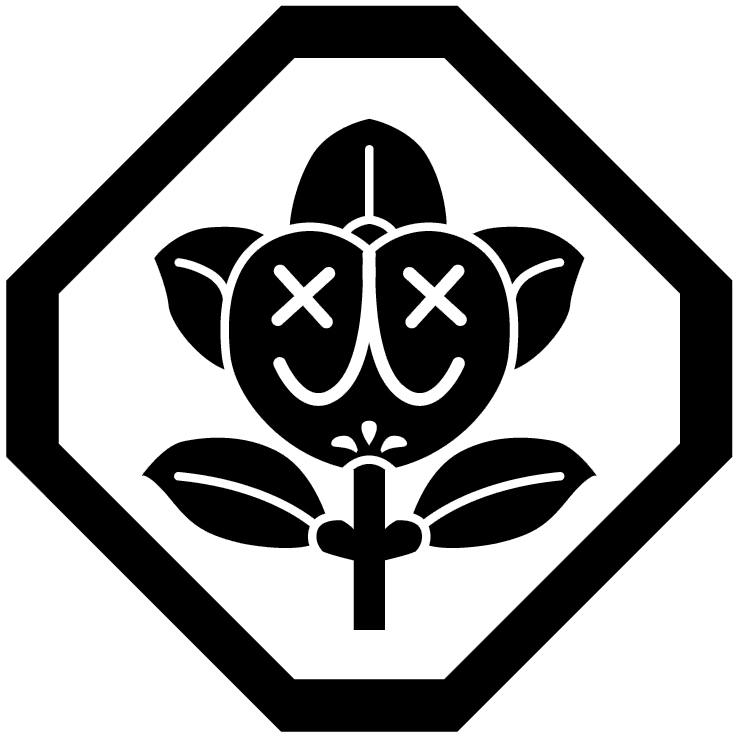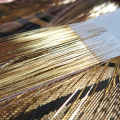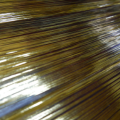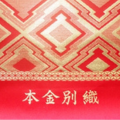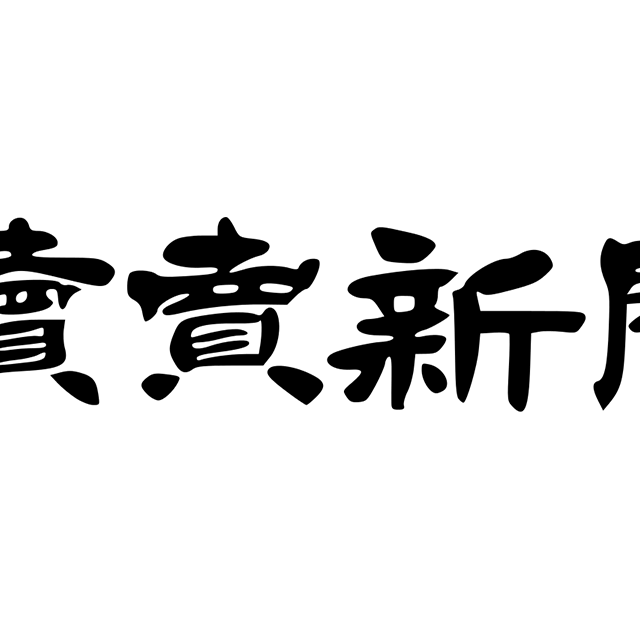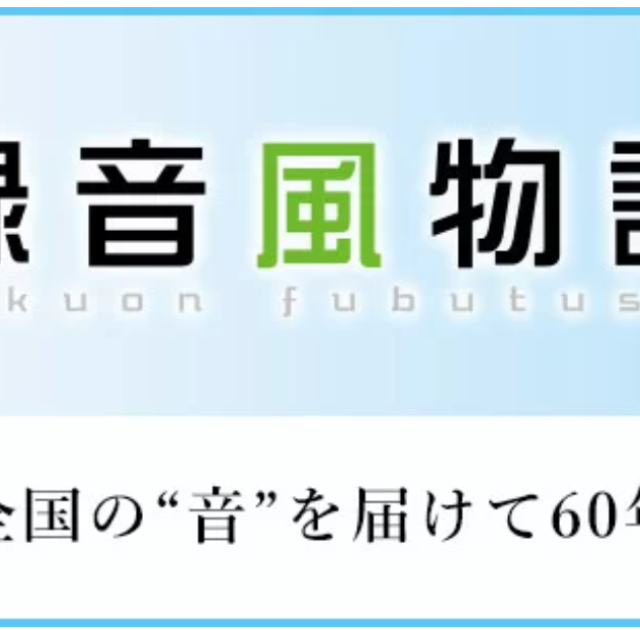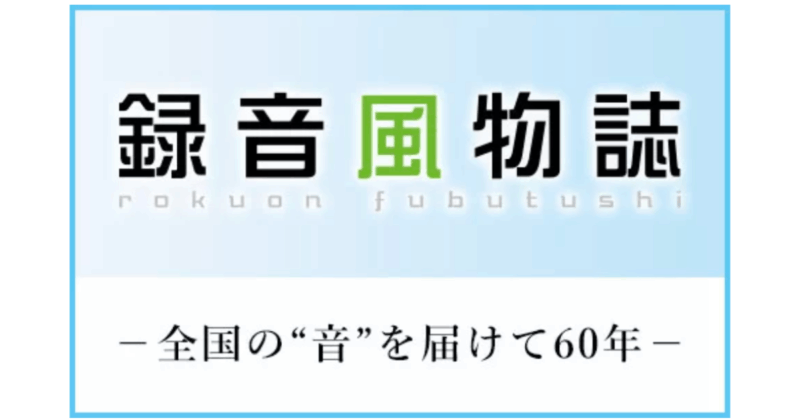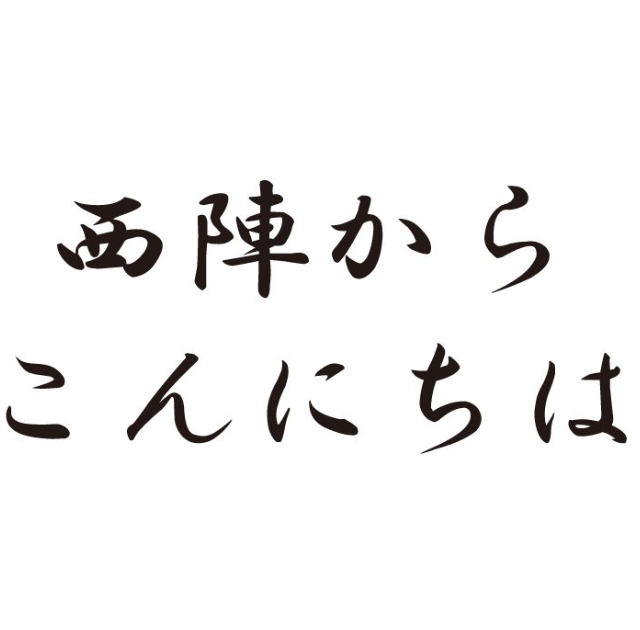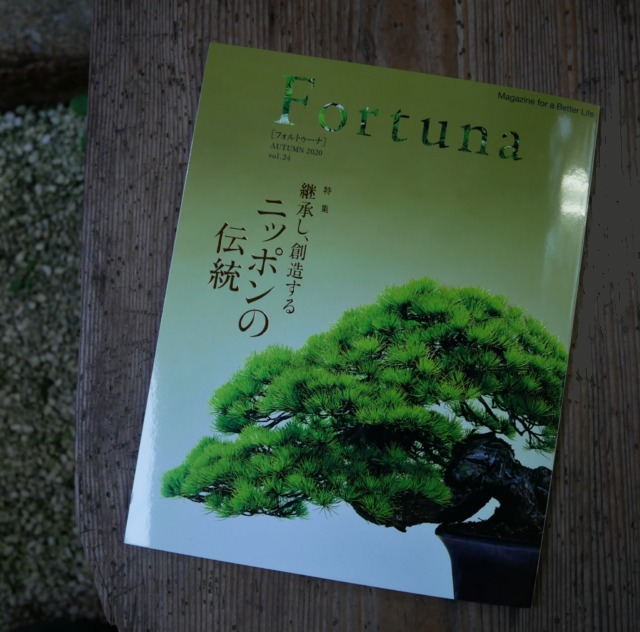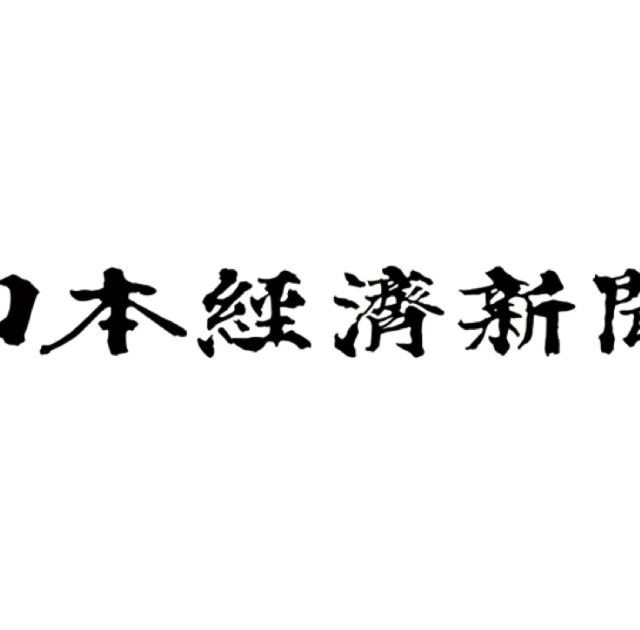KBS京都ラジオ番組「録音風物詩」で西陣岡本が紹介されました
2025年7月、KBS京都ラジオにて放送された番組「録音風物詩 人と糸が紡ぎ織りなす伝統と未来」(制作:ラジオ局編成制作部・森俊輔氏)にて、西陣岡本の取り組みをご紹介いただきました。
番組では、京都を代表する伝統工芸「西陣織」の中でも、特に神社仏閣の装飾に用いられる「西陣織 金襴」に焦点が当てられ、100年以上にわたり金襴を織り続けてきた私たちの仕事や想いを、インタビューと機音(はたおとの録音)を通して丁寧に描いてくださいました。
ここでは、番組内で紹介された職人たちの声を文字起こしでご紹介します。文字起こししずらいので標準語にしていますが、ぜひ、放送の京都弁でお聴きください。
職人の声より
- 金襴とは何か
「主にお寺や神社仏閣向けに使われる織物が“金襴”という部類になります。特別な和紙に漆で金箔を貼った“本金引箔”や“本金糸”などを使い、布地をより金に見せることに特化した織物です。」
— 右記のページから西陣織 金襴についてより詳しくご覧いただけます。 - 機音とともに育った記憶
「うちは何代も織屋をやってきました。子どもの頃は、父が僕らが寝るまでずっと機を織っていて、毎晩毎晩、機音が子守歌みたいに聞こえていました。夜中に目が覚めても、まだ仕事してるんやなって思って。懐かしい音です。」
— 岡本忠雄 岡本忠雄へのインタビュー記事 - 一枚に込める想い
「うちらの品物は、お寺に飾る“打敷”になることが多いです。僕らは毎日金襴を織っていますが、買われる方にとっては一生に一度の買い物かもしれない。だからこそ、傷があれば戻して、その人の気持ちになって織りたいと思っています。」
— 岡本光雄 岡本光雄へのインタビュー記事 - 変わりゆく日常
「昔は一般家庭向けの仏具用品も多くて、私が入社した頃は毎日毎日、検反作業に追われていました。でも今は、そうした一般向けの需要が減ってしまいました。」
— 岡本絵麻 岡本絵麻へのインタビュー記事 - “織る以前”の危機
「西陣織の職人不足と聞くと、若い織り手がいないと思われがちですが、実は“織る以前”の工程に関わる職人がいないんです。ジャガードを作る人も、パーツを専門で作る人も減っていて、『え、それも専業でやってたの?』というような細やかな職人技が支えていたんだと、改めて気づかされました。その人たちがいなくなれば、同じ質の織物はもうできません。」
— 岡本圭司 岡本圭司へのインタビュー記事 - 未来へ向けて
「少しでも興味を持ってもらいたい。知ってもらわないと、“どうでもいいもの”になってしまう。この世界を過去形にしたくないから、今、頑張っています。まずは“織る前の仕事”を増やさなければいけない。そして、職人が誇りを持てるような仕事と賃金を整えていくことが必要です。縁の下の力持ちである人たちに、喜んで取り組んでもらえるような環境をつくっていきたいと思っています。」
— 西陣織について詳しくこちらのページに書いています。西陣織について
番組制作者の声
「以前は、町を歩けばどこからか機織りの音が聞こえてきたものですが、近年はその光景も少なくなってきたと感じます。取材を進める中で、織りの現場だけでなく、機械の整備や素材の調達といった“織る以前”の工程に関わる職人たちの危機に、強い問題意識を抱くようになりました。」
— 西陣出身の森俊輔氏
実際に取材に来てくださった森さんは、織機の構造や整備に携わる職人の存在にも驚かれたご様子でした。私たちにとっては日常の風景であっても、外から見れば「そんなところまで手をかけているのか」と感じられるのかもしれません。
「織機の中の、そんな部分まで専門にしている職人さんがいるのかと驚きました。岡本の皆さんの“どうにかしたい”という気持ちが強く伝わってきました。」
— 森俊輔氏 制作後記より
西陣織は今、まさに過渡期にあります。織りの技術だけでなく、それを支える川上の職人たちの存在が危機に瀕していること。
西陣の職人に焦点を当てたインタビュー記事を掲載しています。
それでもなお、未来へと繋げたいという想いを胸に、私たちは今日も機に向かっています。このような機会を通じて、ひとりでも多くの方に西陣織の魅力と現状を知っていただけたら幸いです。
森さん、そしてKBS京都の皆さま、心より感謝申し上げます。
2025年7月21日~2025年7月27日放送
KBS京都 ラジオ局編成制作部
以下のYouTubeよりご視聴いただけます。
録音風物誌(ろくおんふうぶつし)は、地方民間放送共同制作協議会(通称・火曜会)の加盟局で主に週末に放送されている10分間のラジオ番組であり、「火曜クラブ」時代の1953年から放送を開始して現在も続いている唯一の長寿番組である。一般社団法人・倫理研究所の単独提供。
wikipediaより