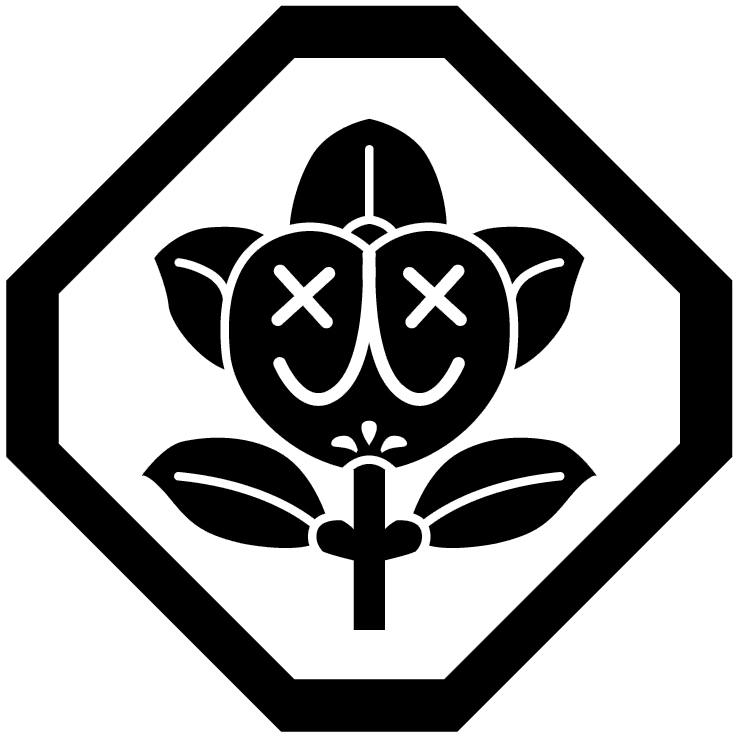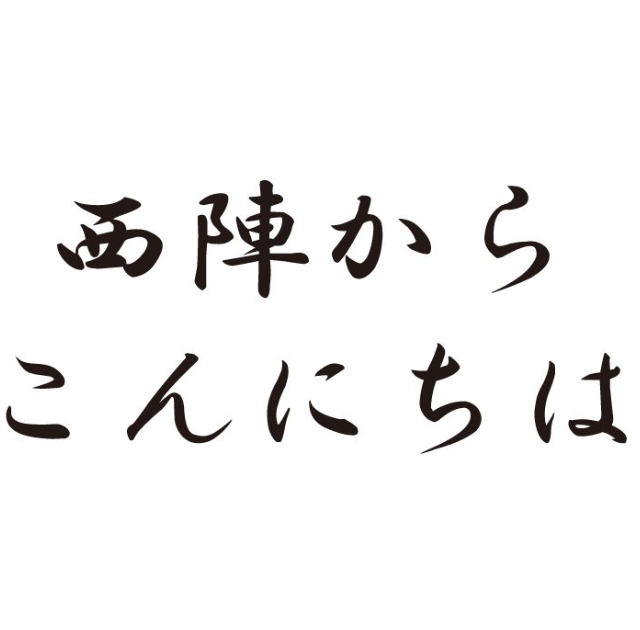西陣織(にしじんおり)は、京都・西陣で伝統的に織られてきた先染め織物です。糸を先に染め、その色の組み合わせで文様を織り出すことで、奥行きのある表情と高い美術性を生み出してきました。その完成には、織屋だけでなく、糸屋・染屋など多くの職人の仕事が欠かせません。
本記事では、西陣織 金襴を支える重要な工程のひとつである「糸染め」を担う、京都・上七軒の染屋「有限会社寺井染工」を訪ね、先染め織物の現場と職人の思いを伺いました。
英語版の記事は以下のリンクから(English version)
西陣織の絹糸の老舗染屋|寺井染工
西陣織は、糸の色で模様を織り出す先染め織物です。当社・岡本織物株式会社(西陣岡本)では絹糸を用いた西陣織を織っていますが、なかでも絹糸の染色工程は、発色と風合いを左右する要となります。
2025年7月23日。京都・上七軒にある染屋「寺井染工」を訪れました。

創業1912年、三代目当主・寺井一雄さんが営む工房は、絹糸を染める熱気に満ちていました。外の気温37.2℃にも関わらず、ボイラーが焚かれる工房内はさらに熱く、まさに「気迫を染める」現場でした。
有限会社寺井染工 寺井一雄さん
「誠実」が宿る染色 一度で色を決める西陣の美学
「誠実に色を染めたい」と語る寺井さんは、絹糸の劣化を防ぐためにも、「一度で色を決める」ことにこだわっています。絹の糸は繊細で、その扱いには高度な職人技と勘が問われます。

記憶に残る西陣の染色風景 「おくどさん」と袋練り
僕が覚えている最初の染屋の景色と言えば、おくどさんです。昔は「おくどさん」と呼ばれる釜で糸を染めてました。通り庭と蔵を改装して大・中・小の釜が3つありました。石炭とコークスが燃料です。当時は袋練りという方法で精練をしていました。今は機械精練です。

袋練りは袋に糸を入れて湯につけるやり方です。綿の袋でした。絹糸にテンションがかからず、糸本来の風合いが保たれる。糸がむっくり(ふっくら)と仕上がり、機械練りとは出来上がりの質が違いました。糸が暴れないよう気を付けながら棒で突いてならす、そのひと手間に熟練の技が必要でした。
染屋の仕事は祖父や父を助けるために入りました。湯気に包まれて暑さに耐える仕事ですから、若いうちに覚えておかないと長くはできません。
染色技能士の資格を取るために、染色工業組合の職業訓練校へ行きました。糸染めの仕事を苦労と感じたことはないです。しかし、絹糸の扱い(捌きや括り)は難しく慣れるのに時間がかかります。今でも糸を扱う時は常に気を遣います。乱れないように整える、それが絹糸と付き合う第一歩です。
西陣の変化と未来 糸を通して見る西陣
色んな仕事をしてきましたが、印象的な事と言えば、皇室関係の儀式の十二単の糸染めや、皇居で育てられた小石丸の染をやったことがぱっと思い浮かびます。お客様から言ってもらえると嬉しい言葉は、「ええ色やった」ですね。

昔と今では絹糸も違います。生繭を座繰りで製糸した糸の仕上がりは扱いやすいしええもんが織れます。しかし、最近は高速製糸や繭の乾燥方法も昔と変わってきたので、絹糸の様子も違ってきました。
最近僕が気になるのは「織屋の人が織物についてあまり詳しくないこと」です。織物について、織屋さんにもっと知ってほしいと思います。プロデュースに重きが置かれる時代だからこそ、素材や技術への理解を作り手自身が深めていくことが必要なんじゃないでしょうか。
今は跡を継いでくれている息子の後輩も入ってきて、工房も賑やかになっています。ほかにも他産地で絹の染めに困っているならなんぼでも協力しています。今まで一緒にやってきた西陣の人たちには「ええもん、たくさん売って盛り上げてください」と伝えたいです。

文化を染める 能との出会いと西陣の染職人の思い
僕は60歳を過ぎてから、お能を習い始めました。
今、なぜ僕が能を習っているのかといえば、能の謡(うたい)の中では、物語の景色や登場人物の心の中に、とても多彩な「色」を見つけることができるからです。
能の経験を通して、日々の暮らしの中でも、より多くの「色」を見つけていこうと心がけています。昔の職人たちは、日常の中で伝統芸能などの文化に自然と親しんでいました。だからこそ、僕よりずっと若い人たちにも、ぜひ伝統芸能の魅力を知ってほしいと思っています。
僕自身も、伝統芸能に関わることで、今の自分の仕事、つまり「伝統的な染の仕事」を、より深く、身近に感じることができるようになりました。
有限会社寺井染工
所在地: 〒602-8383 京都府京都市上京区今小路通御前通東入西今小路町814
(2025年7月23日取材/文・写真・動画 岡本絵麻)
編集後記
西陣織 金襴の織屋、西陣岡本で働く筆者が毎日見て触っている西陣織。西陣織は「先染め織物」であるという前提があります。糸を染めてから糸の色で模様を織り出します。警戒レベルの猛暑日が続く7月下旬、工房の中でマラソンをしたんですか?という位の汗を流しながらカメラを持ってうろつく私を、文字通り熱く、いや、温かく迎えてくださった寺井染工の皆様、お話をしてくださった寺井社長、ありがとうございました。染めの工房から猛暑のはずの外に出たらひんやり涼しく感じたのがとても印象的でした。
お能を習われているお話の中で、「色を探している」というお話。織屋は風景の中に「織」を探し、染屋さんは「色」を探すのだな、と思いました。職業病というか、一生仕事とともに生きるというか。とても面白いです。
当社には、50年〜100年前の西陣織の品を「修理したい」「複製を作ってほしい」といったご依頼で戻ってくることがあります。その際には、新しい糸で織り直す必要がありますが、問題は糸の色です。元々は新品だったはずの絹も、年月を経て色が変化しているため、現時点の「変色した色」に合わせて染めなければ、元の風合いを再現できません。そんな難題にも、染屋さんは真摯に向き合ってくださり、いつも本当に助けていただいています。

西陣織は、京都西陣で培われてきた職人たちの分業によって完成する伝統的な先染め織物です。本記事では、その工程のひとつである染屋の役割と技術をご紹介しました。
次回は西陣織の経糸の整経専門の整経屋さんへのインタビューです。
今までの職人インタビューはこちらからご覧ください。