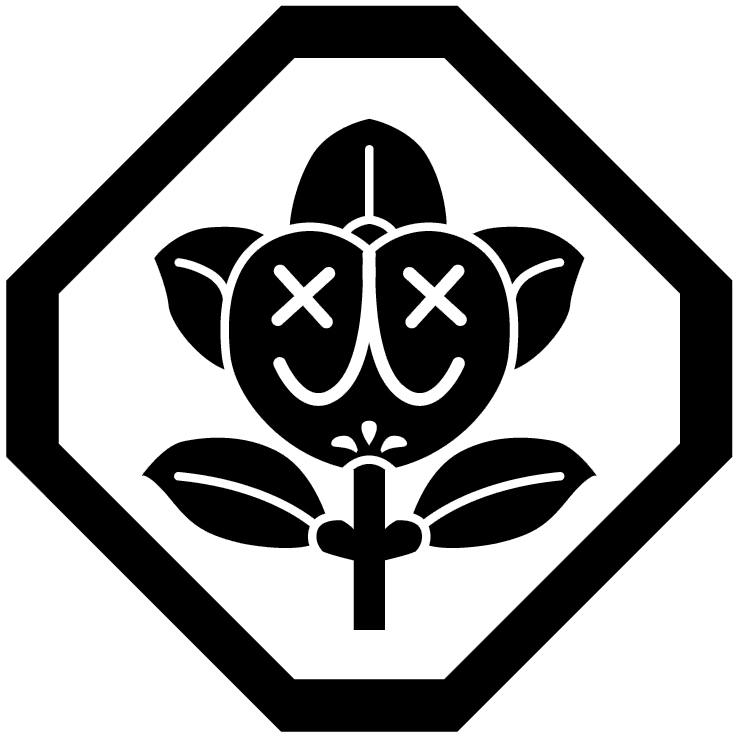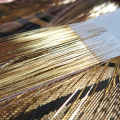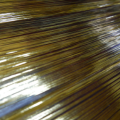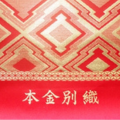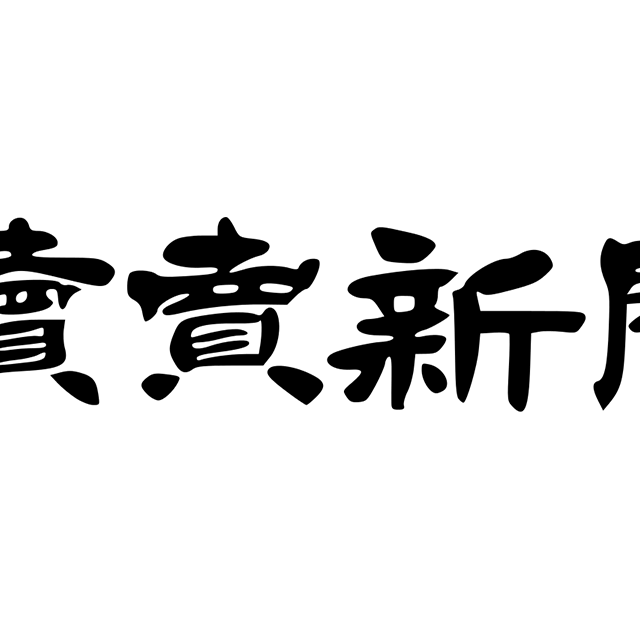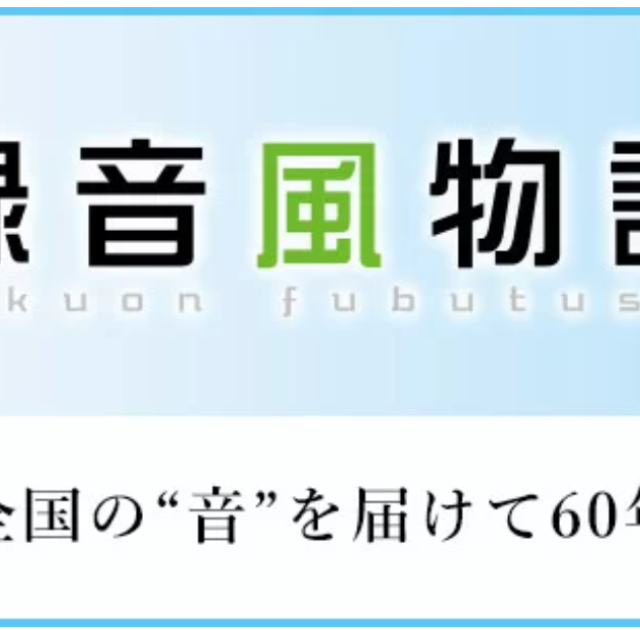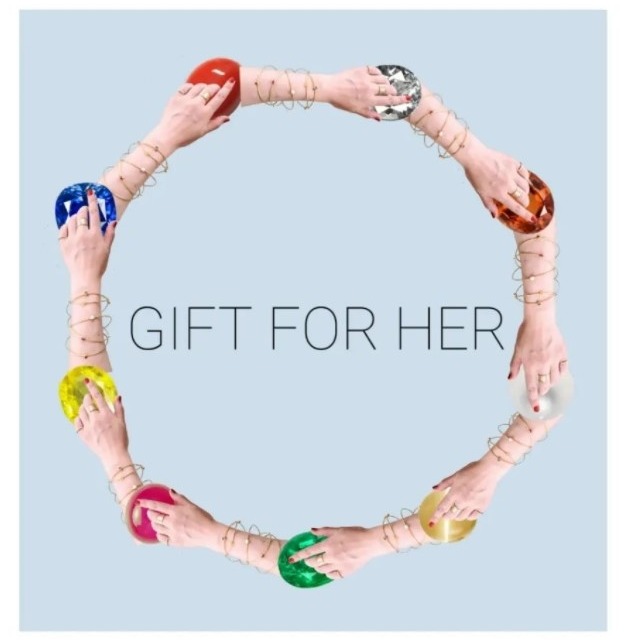こんにちは。
京都西陣にある金襴織屋の岡本織物です。
金襴と言う「金糸・金箔糸」を多用した豪華絢爛な織物を日々織っています。
今日も京都の豪華絢爛なお祭りのご紹介。今頃、路頭の儀と呼ばれる行列が始まるんじゃないかしら。
祇園祭は京都の庶民のお祭りで、葵祭は貴族(賀茂氏&朝廷)による貴族のためのお祭りです。平安時代以来、賀茂御祖神社と賀茂別雷神社の例祭とし行われてきて、日本の祭のなかでも、数少ない王朝風俗の伝統が残されています。
初期は賀茂祭と呼ばれていましたが、江戸時代(1694年)にお祭が再興されてから人々の衣や冠、牛馬、すべてを葵(賀茂御祖神社と賀茂別雷神社の社紋が葵)の葉で飾るようになりこの名がついたとされます。






お稚児さんたち、がんばって牛車を曳いてね!!かわいい~。幼い子供に赤い服を着せたくなる気持ちもわかるわ~。


どうぞクリックして画像をUPさせてください。みんな葵の葉をつけていはります。爽やかですよね。



このお祭りの主人公、勅使代さん。源氏物語の中では光源氏も務めたお役目です。ちなみに勅使(ちょくし)とは、皇帝・天皇・王など国の元首が出す使者のことでございます。↓勅使のお馬さん、白馬殿の飾りがかわいいです。


5月といえども暑い日は暑いです。お稚児さんは笠の下に入っていただきましょう。綺麗な金襴地に山吹の花笠にウコン色の男性の装束、赤いお稚児さん。なんて綺麗なんでしょう。


京都御所の南側、建礼門のところの広場。普段はここには「自転車道」という自転車で出来た獣道状の線が一本・・・ありますね。お祭りの時には馴らさないんだ。時々線を消してはるところを見かけるのですが・・・。



金襴地の着物たち。




お琴でしょうか。


足元も、いい感じです。結構歩きやすいとのお話を聞きました。



色々と宝物を持って歩きます。

刀入れ。虎・・・?


葵はこのように烏帽子についています。



風流傘の中に男性が4人はいって何かごにょごにょ。4人で満員ですね。


男性もこの色の組み合わせ。洋服ではなかなかありませんが着物だと無理なく年配の方でも着こなせる色です。素敵。




命婦と呼ばれる高級女官。小桂(こうちき)をきてはります。



女嬬さんという食事をつかさどる女官さんたち。


なんて華やかなんでしょう。

平安時代には内親王から選ばれた斎王代。現在では市民から未婚の女性が選ばれるので、斎王の代り「斎王代」と称されています。十二単(じゅうにひとえ)の大礼服装を着用し、腰輿(およよ)という輿に乗って下鴨神社、上賀茂神社へ参向しはります。

女の子達もかわいおす~。



華やかな着物に胸に飾った葵の葉がほんまに「さつき」にぴったりです。



斎王代の姿↑

駒女(むなのりおんな)と呼ばれる女性達。駒は馬のこと。斎王に付きそう巫女(みかんこ)で、騎馬でつきそうので駒女と呼ばれます。








これでざくっとした葵祭の「路頭の儀(行列)」の説明を終了。ざくっとしすぎでしょうか。
勅使をはじめ平安貴族そのままの姿で京都御所を出発しはります。
総勢500余名、馬36頭、牛4頭、牛車2基、輿(およよ)1台の絢爛豪華な王朝絵巻が下鴨神社、上賀茂神社へ向かいます。この写真は2013年の写真です。
さて、今日の葵祭りはどのようになりますことやら。御来京の皆様、どうぞお楽しみください。